同じものに対する2つの描き方/Different pictures for the same theme
( English text continues to the latter half of the page)
60年代末にジョニー・ミッチェルが発表した『Both sides now』という曲がある。一見すると地味だが時代を超えて歌われる名曲だ。
《Rows and flows of angel hair
And ice cream castles in the air
And feather canyons everywhere
I’ve looked at clouds that way
But now they only block the sun
They rain and snow on everyone
So many things I would have done
But clouds got in my way
I’ve looked at clouds from both sides now
From up and down and still somehow
It’s cloud’s illusions I recall
I really don’t know clouds at all》
《空にはアイスクリームの城が浮かび、天使の羽が谷間を作り、
天使の髪がその周りを流れる。
空に浮かぶ雲は幼い私の眼にこんな風に見えていた
でも今、雲は太陽を遮り、そこら中に雨や雪を降らす
私のやりたかった多くのことは今になって雲に遮られている
雲には表と裏があり、上と下の両面(Both sides)がある
ふと想い出した雲の記憶に、私は何も理解していなかったことを知る
(一部意訳を含む拙訳)》
物事は一つの意味しか持たないわけではない。同じものでも両サイドの意味があることを理解するのが大人になるということだ。また、同じように見えるものが実はまったく別の意味を人生に与えることがある。
前回に続いて映画にテーマを求めます。今回は同じテーマを扱いながらも、まったく違うメッセージを孕んだ二つの映画を取り上げます。
大人のおとぎ話『I am Sam』
『アイ・アム・サム(I am Sam)』は2001年公開のアメリカ映画。主人公のSamを演じたショーン・ペンはアカデミー主演男優賞にノミネートされ、娘役のダコタ・ファニングも放送映画批評家協会賞を始め、数々の賞を受けた。
サムは知的障害を持つ中年の男。福祉事務所からはその知能レベルを7歳程度と認識されているが、スターバックスの店舗で常連客に愛されて明るく働いている。ある日知り合いの娼婦に「お前の子」だと言われた赤ん坊を置いて行かれて、それ以来自分の娘だと信じてダコタ・ファニング演じるルーシーと楽しく暮らしている。ルーシーは幼いながらもサムを愛する聡明な子に育つ。だが彼女が7歳になった時に彼女の知的レベルはとうに父親を追い抜いてしまい、ソーシャルワーカーは養育能力がないと判断したサムから彼女を引き離し施設に入れようとする。知的ハンディキャップを抱えて社会に認められないサムが決意したのは法廷での闘い。そこにたまたまミシェル・ファイファー演じるリタというエリート弁護士が登場、社会問題に関わる弁護をして弁護士としてのランクをアップさせようとしてサムの弁護を引き受ける。ところがサム側の証人で知的障害や精神不安を抱えた友人たちは法廷の場で検察官にやり込められて次々とパニックを起こしたり、深い鬱を抱えたりする。弁護士のリタ自身も圧倒的に不利な裁判の中で、やはり周囲から懸念されたように自分には社会問題は扱えないのか、と思い悩む。本来ならはるかに知的水準の低いサムが優しくリタを抱きしめ慰める。いずれの場面も、知的レベルの高い検察官や裁判官が冷たい社会のシンボルとなり、打ちひしがれた弱者に対して知的障害を持つサムがまるで天使のように癒しを与える役どころとなっている。ここで扱われる知的障害のイメージは「純粋」、「神の愛でし幼子」のシンボルのようだ。
もちろんこの映画はハッピーエンドで終わる。杓子定規な判断を押し付ける検察官の間でも徐々にサムの純粋と懸命に心を打たれるムードが広がり、最終的にルーシーは善意あふれる里親に預けられて、しかもサムはそのすぐ近所に引っ越して毎日のようにルーシーに会えるようになった。その二人の姿とそこに存在する愛の深さに周りの大人たちは気づき暖かい眼で見守る。映画のラストシーンはルーシーや子供たちと公園で一緒に遊びはしゃぐサムの幸せいっぱいの笑顔で幕となる。
もちろんこの映画は純粋なる“大人のおとぎ話”。世間がそうそう善意だけで作られているわけではない。それでも劇中に流れる数々のビートルズのナンバーが奏でる素敵なストーリーであり、こんな映画ももちろんあり、だと考える。

消えゆこうとする知能があまりに悲しい『アルジャーノンに花束を』
自分もそうだったが、この作品はまず小説として読んだ方も多いのではないか。『アルジャーノンに花束を』はもともとダニエル・キース(多重人格を扱ったドキュメンタリー「24人のビリー・ミリガン」の著者)の小説。そして映画としては『Charly(邦題:まごころを君に)』というタイトルで1968年に公開されている。
主人公は6歳程度の知能しか持たない青年チャーリー・ゴードン。夜間学校で読み書きを習っているものの自分の名前もろくにスペリングできない。その低い知能のために両親は不仲となり母親は彼の障害を受け入れることができない。彼の少年時代を彩る風景は暗いものしかない。パン屋の下働きをしている職場でも同僚に馬鹿にされ、なけなしの給料を騙し取られる。しかし知能の低さゆえ、自分がどれだけ悲惨な境遇にあるのかもよく理解できていない。この導入部では精神遅滞は不幸で暗い人生の象徴となっている。
そんな生活の中でチャーリーは夜間学校で、知能の急速な発達を促す頭部への実験的な外科手術を勧められる。小説の表題のアルジャーノンはその外科手術の実験体となった1匹のハツカネズミの名前。大学の実験室でチャーリーとアルジャーノンは同時に迷路のパズルを解こうとする。あっさりと負けてしまったチャーリーは「僕はネズミより馬鹿だ」と言って泣き崩れる。彼が知能の低さを心から悲しいと思った初めての瞬間であり、外科手術を受ける決心をした瞬間だった。
脳への外科手術を受けてから、実験体のアルジャーノンそのままにチャーリーの知能は飛躍的に進化を遂げる。もはや馬鹿にできる相手ではなくなってしまって同僚たちの視線は冷たいが、大学教授以上のレベルに進化した彼の知能を活かして大学で研究の一翼を担う。人格は子供のままだが、社会に認められた彼は新しい仕事を得、恋人も現れ人生の喜びを享受する。そうした日々の中で彼の胸に去来するのは、かつては自覚できなかった自分自身の惨めな日々。二度とあそこには戻りたくない、との想いがチャーリーの心に湧きあがる。
ところが実験室の中で“友達”になっていたアルジャーノンに異変が起きる。異常行動が目立つようになったかと思うと、実験結果も明らかに悪化していく。チャーリーは悟る。あの手術の効果は一時的なもので、いずれは自分の知能も元のレベルに戻っていく!二度と戻りたくなかったあの人生に舞い戻るのは絶対にいやだ、とばかりに彼は日夜新たな解決策を求めて研究に没頭する。その一方、生涯で初めての恋人に別れを告げるなど、来るべき運命に諦めも見せている。知識が徐々に消えていき、頭の中には白い靄が広がる。運命に必死に抗う姿は悲壮そのものだ。
小説では彼自身が記した文章をそのまま出版したという設定になっている。冒頭はまるで3歳児が書いたような幼く間違いだらけの文章が、知能が発達を遂げるのに伴い文章も立派な大人のものになっていく。それだけに終盤に近付くにつれて段々文章にミススペリングが増え、最後には再び幼児の文章に変わっていき、最後の一文『どーかついでにあったらうわ にわのアルジャーノンのおはかに花束をそなえてください(原文:P.S. please if you get a chanse put some flowrs on Algernons grave in the bak yard.)』がどうしようもなく切なく響く。映画ではとうとう元の知能レベルに逆戻りしたチャーリーが近所の公園で子供と遊んでいるところを、別れた恋人がじっと見つめるラストシーンとなっている。そこには『アイ・アム・サム』のラストで見られた幸せな笑顔はない。どうしようもなく悲しいラストだ。ここまで想い出してみてふと思いついたのは、ひょっとしたら『アイ・アム・サム』の監督はこの悲しいラストシーンのアンチテーゼとして同作のラストを作ったのかもしれないというもの。
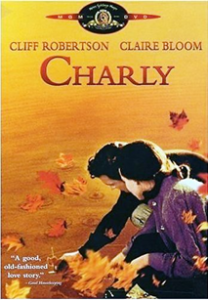
アルツハイマーの物語はブームになり得るのか
どちらも精神遅滞を扱った作品でありながら、その内容は光と影ほどにも違う。どちらの方が自分の心に染みるのかを問われれば、それは何と言っても『アルジャーノンに花束を』の方だろう。自分の頭からこれまでに培った知識や経験が流れ出ていくのを止められないのは恐怖以外の何物でもない。この映画と原作は「脳への外科手術」というSF的なツールを使いながら、知能に存在価値を見出す人間の根源的な恐怖を描いていた。
前回も書いたことだが、ヒットする映画の条件はその時代が求めるテーマを孕んでいるかどうかというのが自分の説だ。現在の日本が抱える問題は急速に訪れる人類が未体験の未曽有の高齢化社会。多くの人々が加齢とともに恐怖を覚えるアルツハイマー症候群。そうしたところからアルツハイマーによって記憶が流れ落ちていく根源的な恐怖と、そこから生まれる救いのようなストーリーが今後生れないだろうか。アルツハイマー症候群を扱った映画としては、日本で渡辺謙主演の『明日の記憶』、アメリカではジュリアン・ムーア主演の『アリスのままで』があった。しかしどちらの映画も最後は主人公の記憶と人格を喪失したままでラストを迎える。そこには主人公の周囲や家族の愛情はあっても、主人公本人にとって救いはない。正直に言ってどちらの作品もラストにやるせないものを感じるしかなかった。これではこのテーマがブームになるとは思えない。もしも病状の進行とともに主人公に救いが訪れるようなストーリーが産み出されれば、時代に残る作品になり得るかもしれない。
“Both sides now” is the number that Joni Mitchell made in the end of 60s. This simple melody song is classical number sung beyond generations.
《Rows and flows of angel hair
And ice cream castles in the air
And feather canyons everywhere
I’ve looked at clouds that way
But now they only block the sun
They rain and snow on everyone
So many things I would have done
But clouds got in my way
I’ve looked at clouds from both sides now
From up and down and still somehow
It’s cloud’s illusions I recall
I really don’t know clouds at all》
Things have both aspects. The same thing can offer totally different factors to your life and to recognize this means growing up.
I seek the theme into movies again. This time I like to introduce 2 movies which give you different messages though they handle the same theme.
Adults’ fairly tale “I am Sam”
“I am Sam” is an American film release in 2001. Sean Penn played the main roll, Sam, and was nominated as Academy award for best actor. Dakota Fanning played his daughter, Lucy. She won various awards like Critics’ Choice Movie Awards.
Sam is middle aged man who has mental retardation. His intellectual level was regarded as 7 years level by the social office. But he was positively working in Starbucks loved by many customers. One day a hooker left a baby at his house saying that she was his baby. After the day he had brought up the baby as his daughter and Lucy had grown up to wise girl who loves Sam. However her intellectual level surpassed the father when she became 7 years old. Social workers forced him to leave Lucy to social facility which he never wanted to. Sam decide to file a suit. Then Rita, elite lawyer played by Michelle Pfeifer, was appointed the case. She attempted to enhance her reputation by committing social case. But Sam’s friends who have problems like mental disorders fell into panic at bar. And Rita herself was troubled with her skills in absolutely disadvantageous trial. Sam whose intellectual level is far below Rita’s hugged her and heal her. Any scenes describe prosecutors and judges with high intellectual level as a symbol of cold society. And Sam is described as an angel of healing. The impression of mental retardation is taken here as “purity” or “God loved child”.
Off course this film finishes in happy ending. Even prosecutors who go by book started recognizing Sam’s pure and intense attitude and Lucy was finally adopted by benevolent foster parents. Sam moved to their house and he could see Lucy every day. People recognized the deep love and bond between Sam and Lucy. The last scene of the film was Sam’s laughing face with a full of happiness playing with Lucy and other kids in the park.
Off course this is the fairly tale for adults. This world is not filled with only bona fides. But this film rolls on fantastic story along familiar songs of Beatles. This film is also worth while viewing.

Intelligence fades away pity and sad “Flowers to Algernon”
Quite many people knew this story as a novel like me. “Flowers to Algernon” is the novel by Daniel Keyes (the Author of “The minds of Billy Milligan”) and as a movie “Charly” was released in 1968.
Charly Gordon is a young man whose intellectual level is 6 years. Even though he learns read and wright in the night school, he can’t spell even his name. His mental disability made his parents divorced. His mother cannot accept his disability even now. His young days are illustrated with only sad and dark colors. He is now working in the bakery as an assistant job but his colleagues make fool on him and cheat his small salaries. However he doesn’t understand how miserable his surroundings are. In these introduction scenes, mental retardation is described as a symbol of unhappy and misery life.
Charly was encouraged to take surgery operation to his brain which could make great leap of his intelligence. Algernon is the experience mouse of this operation. Charly competed maze quiz with Algernon and lost quickly. “I am much more foolish than a mouse”, he cried laud and recognized how his disability is sad. He decided to take the surgery operation to his brain.
After the operation, his brain made a great jump. His colleagues were not happy as Charly is no more target of fooling around. Although his personality stays that of child, Charly acquired the brain more than professors and he joined research activities at college. He acquired new occupation, social position, and even the lover. He enjoys the joy of life. His miserable life is already the past and he never wants to go back there.
His friend in the laboratory was Algernon but Algernon started abnormal behavior and his intellectual level also deteriorated. Charly understood the whole thing. The surgery operation takes effect just temporally and my intelligence is going back to previous level! He immersed himself to experiment to change the destiny. On the other hand, he said goodbye to his lover which seems to give up his destiny. His intelligence is fading away day by day and something like white haze spreads in his brain. His appearance to protest the destiny is nothing but pathetic.
The novel took the style as if Charly himself wrote it. In the beginning texts are full of miss spelling and infant sentences like a little child. These texts gradually are improved page by page. When a reader reaches the middle part, all sentences are totally mistake free and refined. So reader would be deeply impressed, when he reads the last sentence of the novel: “P.S. please if you get a chanse put some flowrs on Algernons grave in the bak yard”. The last scene of the film is the scene in the park. Charly has gone back to previous intellectual level and he played with children in the park. His former lover is watching them at sad look. It was so sad last that there is no salvation in the scene. The director of “I am Sam” might have tried to make the last scene of the film as an antithesis of Charly.
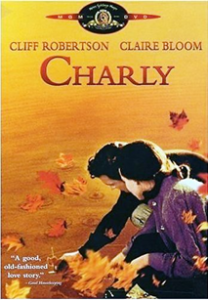
Can the story of Alzheimer become a boom?
Both works handle the theme of mental retardation but their impressions are so different like light and shadow. Which one gives stronger impressions to my heart? That must be “Flowers to Algernon” which described the fundamental fear of intelligence and experiences of life fading away.
As I wrote in previous article, big hit movies must contain the theme of the time. The most critical issue of latest Japan is the unprecedented aging society which human beings have never experienced. Then the fear of cognitive impairment and salvation to patients can appear in near future? There already had been films like “Still Alice (2014, starring Julianne Moore)” or Japanese film “Ashita no Kioku (2006, Memories of Tomorrow starring Ken Watanabe) which handle Alzheimer syndrome. But in both movies main characters lost their memories and personalities at last and no salvation for the patients themselves even though there were love of families. I couldn’t help feeling something downhearted and these inconsolable films cannot be the film of times. If stories like salvations visit patients as symptom goes on, the film can be the film of the time.
